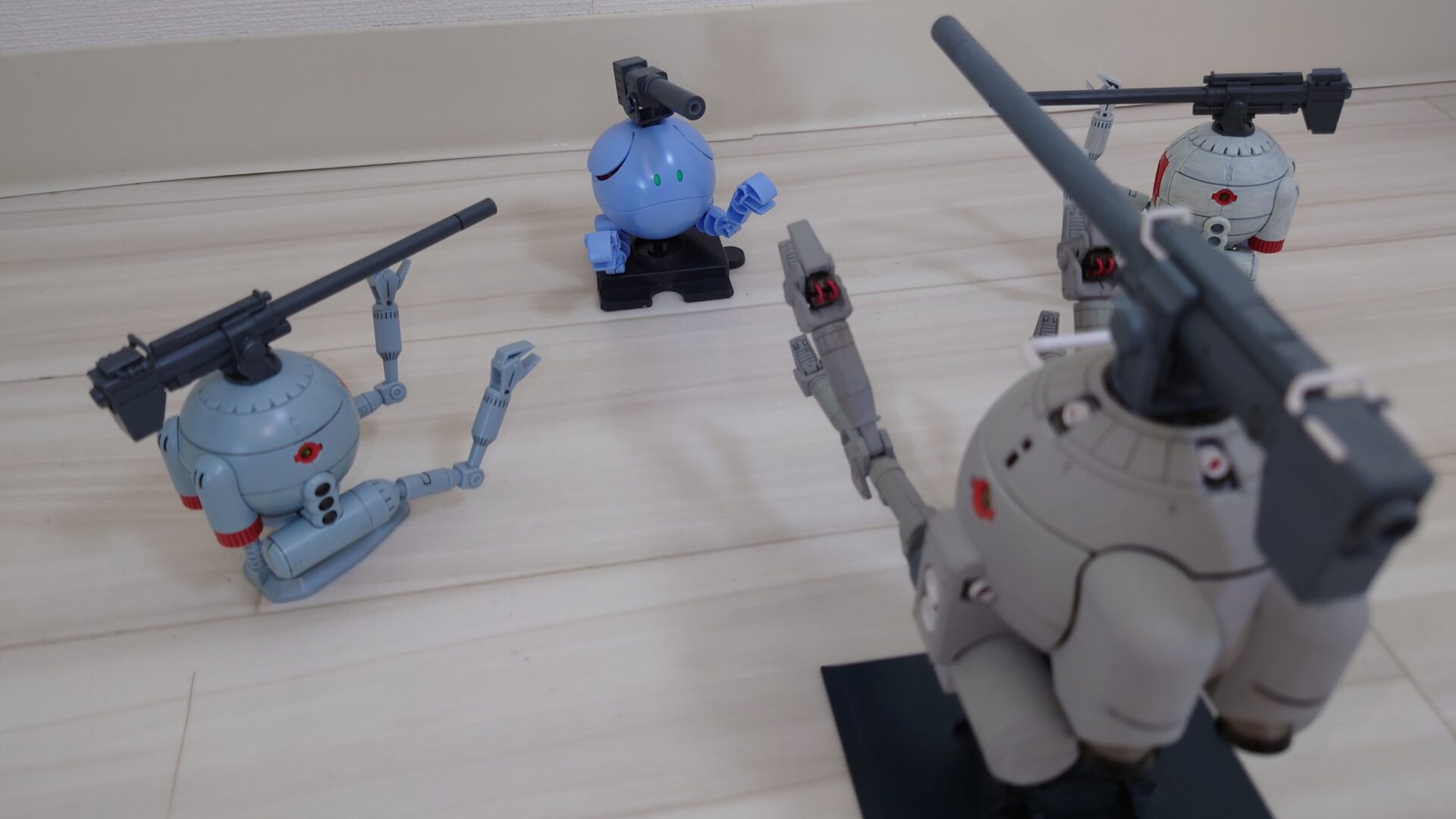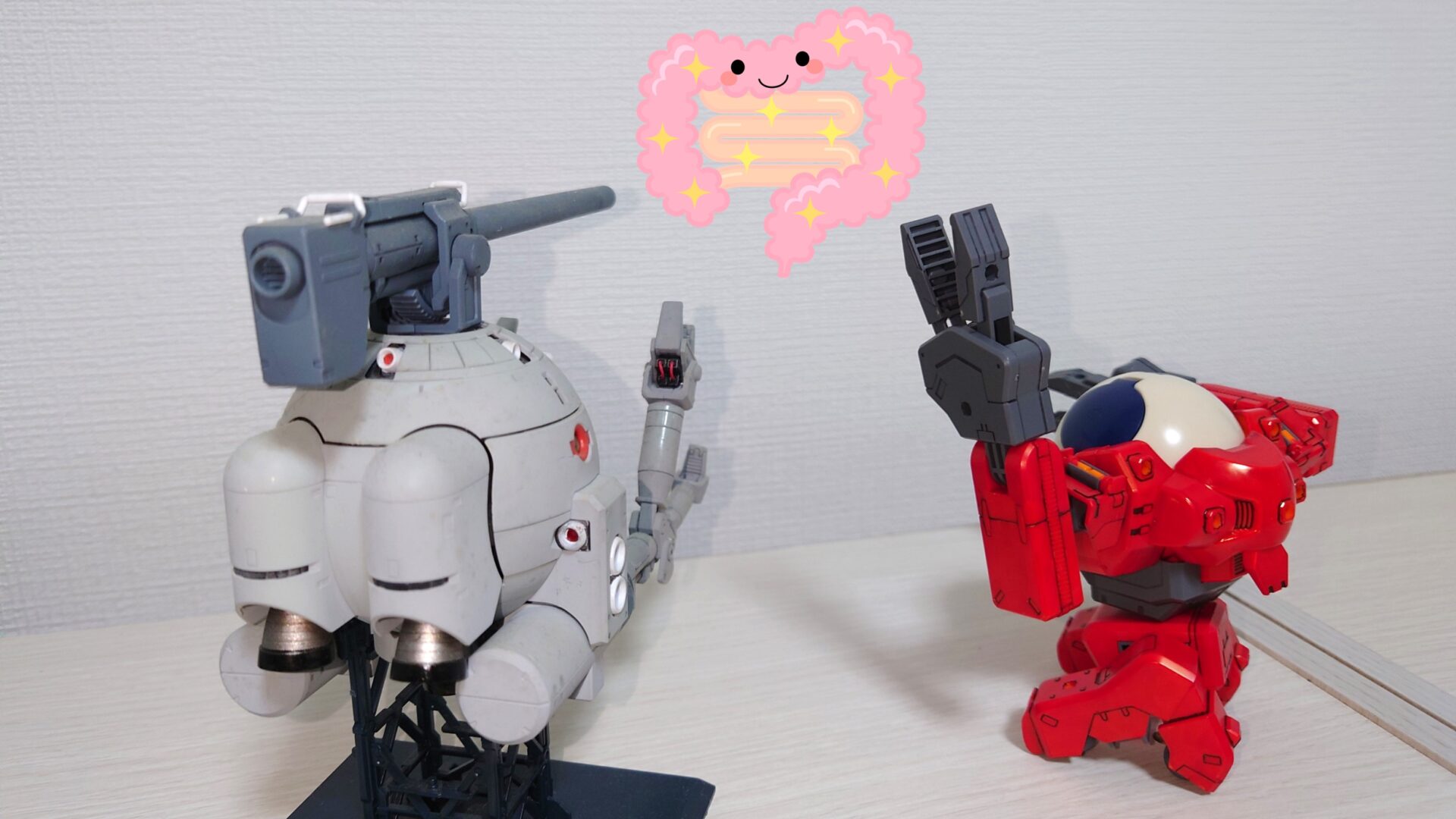集中力の育て方 #5【中級編:思考発話】

セルフトーク(思考発話)は、自分への言葉掛けで集中力とメンタルを整える方法である。ポジティブ・指示的・モチベーション型を状況に応じて使い分けることで、競技や学習のパフォーマンスを高められるだろう。
集中力の育て方 #5【中級編:思考発話】
今回は直接スポーツに役立てられる、集中力の育て方のひとつ「思考発話(セルフトーク)」について、紹介する。
思考発話(セルフトーク)とは
セルフトークとは、アスリートが自分自身に向けて行う内面的な言葉や自己対話を指す。
スポーツ心理学では、セルフトークを活用して集中力を高めたり、緊張を和らげたりする重要なメンタルトレーニングの一環として広く活用されている。松岡修造氏の「できる!できる!!」のように、アスリートが自分の心の中で思ったことを声に出すことが重要である。
あくまでもこれは、自分が自分自身に向けて行うもので、他人からのフィードバックとは異なる。
なぜ思考発話が良いのか
一流のアスリートは、思っていることを口に出す傾向が強いことが研究によって確認されている。特に、リアルタイムで思考を言語化することで、高い集中力を維持できるとされている。
例えば、ゴルフや野球のように、判断に余裕がある競技においては、思考を口に出すことでパフォーマンスの向上が期待できるだろう。
なぜ思考発話が集中力を向上させるのか
なぜならば、「メタ注意力」をブーストするからである。グラスゴー・カレドニアン大学の最近の研究では、アスリートに心の中での自己対話を言語化するように指示したところ、思考発話を行った参加者は集中力が大幅に向上した。
この研究では、「集中力」を「さらなる情報の処理を行うために、もっとも大事なデータに焦点を当て続けること」と定義している。当然「集中力」は、スポーツのパフォーマンスを上げるための前提条件だ。スポーツ選手が効果的に集中するためには、意識・知識・注意をコントロールできねばならない。意識・知識・注意のコントロール能力を育てる方法のひとつが、この「メタ注意力」を使うことである。
・詳しくはこちら
→知覚・注意・視線から学ぶ、見ること【身体運動学的分析】
「メタ注意力」という言葉は馴染みがないが、簡単に言うと「注意に関する意識・知識・コントロールの3つを組み合わせたもの」だ。これをスポットライトに例えると、以下のような要素が考えられる。
- 意識:現在、スポットライトが何を照らしているのかを理解している状態
- 知識:スポットライトを切り替えたり、照らし続けたりするための方法を理解している状態
- コントロール:スポットライトを実際に操作できる状態
すなわち、この3つの要素が揃っていると、その人は「すごい集中力をもっている」と評価されやすくなる。
セルフトークは、集中力を高めるための非常に有効な手法であり、意識・知識・注意をコントロールしやすくなることにより、パフォーマンスの向上が期待できる。ぜひ、練習に取り入れてみて欲しい。
思考発話の効果
セルフトークは、アスリートや学習者にとって強力なツールである。
①ストレスへの耐性向上
リバプール・ジョン・ムーアズ大学の研究では、エリートゴルファーのプレーに観察が行われた。その結果、高いプレッシャーの中でパフォーマンスを発揮する際、特にパッティング直前にスキルが高いゴルファーは、練習時よりも技術的なポイントを声に出して確認することが多いことがわかった。
このセルフトークによって、選手は自分の思考プロセスを明確に識別し、自らのパフォーマンスを客観的に分析することが可能になる。この自己観察力が、結果的にプレッシャーに強くなる要因となるのだ。頭の中で孤独に考えるだけではなく、声に出すことで客観性が生まれ、冷静に戦況を把握できるようになるだろう。
②学習効率の向上
セルフトークはアスリートだけでなく、教育の分野でも長い間利用されてきた。この手法が持つ主なメリットには、以下のとおりである。
- 理解力の向上:テキストや資料を声に出して読むことで、内容がより深く理解できるようになる
- 読書スピードの向上:声に出して読み上げることで、情報の処理が効率化され、結果的に速読が可能になる
- 問題解決能力の向上:思考を言葉にすることで論理的な思考がクリアになり、問題解決がしやすくなる
アスリートだけでなく、学習者や一般の人々もこのツールを取り入れることで、より良い成果を得ることができる。正しい考え方と適切な声掛けによって、あなたのパフォーマンスはあなた自身の言葉によって、大きく変わることだろう。
思考発話の種類
セルフトークには、さまざまな形式があるので、ここでは代表的な種類について詳しく説明する。
①ポジティブセルフトーク
ポジティブセルフトークは、自信を高めたりモチベーションを向上させたりするための肯定的な言葉。この形式のセルフトークは、プレッシャーを軽減し、集中力を高める効果がある。
例えば、「自分ならできる」「大丈夫だ」「落ち着いていこう」など、松岡修造氏の格言のように、ポジティブな自己信念を強化する言葉が有効である。
②指示的セルフトーク
指示的セルフトークは、技術や動作に焦点を当てた具体的な指示を自分に与える言葉。これにより、新しいスキルを学ぶ際や複雑な動作を行う際に、具体的な行動を促すことができる。
例えば、「リラックスして」「次の動きに集中しよう」「膝を曲げて」「リズムを意識しよう」など、具体的な指示が、一連の動作を円滑に進める助けになる。
③モチベーションセルフトーク
モチベーションセルフトークは、やる気を引き出すための言葉を使う。このタイプのセルフトークは、特に困難な状況において自分を奮い立たせるのに役立つ。
例えば、「最後まで諦めない」「全力を尽くそう」など、前向きな言葉が自分を励まし、エネルギーを与えてくれる。
④ネガティブセルフトークの抑制
ネガティブなセルフトークは集中力を妨げ、更なるミスを引き起こす可能性がある。ネガティブな思考を抑えるために、ポジティブな言葉に自ら置き換える。
例えば、「失敗したらどうしよう」→「挑戦してみよう」、「またミスをするかも」→「次はうまくできる」など、ネガティブな考えをポジティブなものに変えることで、自信を持った行動が促される。
思考発話の効果的な活用方法
①ポジティブな言葉を選ぶ
ネガティブな表現は不安を増幅させる可能性があるため、「失敗しないように」ではなく「成功させるために」といった肯定的な言葉を用いることが重要。
②短く具体的な言葉を使う
セルフトークは短く、覚えやすいフレーズの方が効果的です。例えば、「リラックス」「集中」「次」といった簡潔なフレーズを意識する。
③日常的に練習する
セルフトークは試合中だけでなく、日常の練習から取り入れることで効果が高まる。常日頃からポジティブな思考パターンを形成することが、成功の鍵になるだろう。
④一人称VS三人称
集中力を高めるためには、状況に応じて一人称と三人称のセルフトークを使い分けるのが良いだろう。
一人称のセルフトーク【メリット】
自分自身を鼓舞する際に、より直接的で感情に訴えかけることができる。目標達成へのモチベーションを高めやすい。
一人称のセルフトーク【デメリット】
感情が先行しやすく、客観的な視点を持ちにくい。プレッシャーを感じやすく、集中を妨げる可能性がある。
三人称のセルフトーク【メリット】
客観的な視点を持てるため、冷静な判断や問題解決につながりやすい。感情的な距離を取ることで、ストレスや不安を軽減できる。
三人称のセルフトーク【デメリット】
他人事のように感じてしまい、モチベーションを維持しにくい場合がある。自分へのコミットメント(責任・約束)が弱まる可能性がある。
セルフトークは、自信を高めたり、プレッシャーに強くなったり、モチベーションを引き出すための強力な手段である。さまざまな種類のセルフトークを使い分けることで、パフォーマンスの向上やストレスの軽減が期待できるからだ。日常生活に取り入れ、継続的に実践することで、その効果を実感できるだろう。
まとめ:集中力の育て方 #5【中級編:思考発話】
スポーツ心理学における思考発話(セルフトーク)は、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮するために非常に効果的な手法である。一流のアスリートが実践するように、リアルタイムで思考を言葉にすることで、意識・知識・注意をコントロールしやすくなるだろう。また、セルフトークを状況に応じて使い分けることで、パフォーマンスの向上が期待できる。
日常生活や練習に取り入れ、継続的に実践することで集中力を育て、その効果を最大限に活用して欲しい。
【参考文献】
(Amazon)理想の自分をつくる セルフトーク・マネジメント入門【鈴木義幸】
(Amazon)おしゃべりな脳の研究【チャールズ・ファニーハフ】