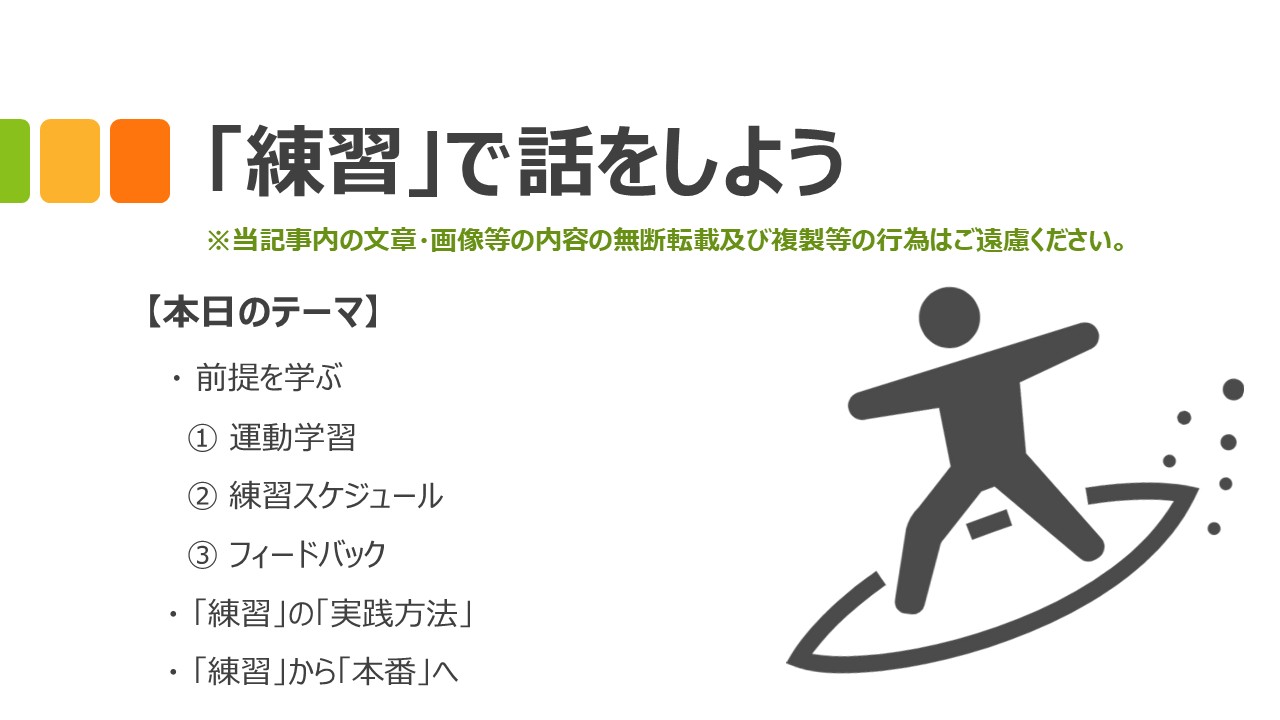疲労回復と睡眠 #3【習慣編】

良い睡眠は“反復で作るスキル”。就寝・起床を固定し、夜は刺激(光・食事・カフェイン・アルコール)を減らす。朝に日光を浴び、週4回以上の実践で2か月を目安に定着。アイテムや環境に加えて、習慣の設計がリカバリーの近道となる。
疲労回復と睡眠 #3【習慣編】
スポーツ競技者にとって、疲労回復は非常に重要である。そして、我々の人生の三分の一は睡眠時間である。アイテム、環境を整えた後は、良い習慣としての睡眠を身に付けていかなければならない。
習慣については『集中力の育て方 #2【初級編:ネットファスティング】』でも書かせてもらっている。そちらもぜひ、参考にして欲しい。
では、どうすれば習慣化できるのかを紐解いていく。
習慣形成における「報酬」と「反復」
習慣を形成するために必要なのは「報酬」か「反復(繰り返し)」なのか?
多くの習慣形成に関する書籍では、①何かを達成した後に自分にご褒美を与えることの重要性、②一つの行動を無意識に続けられるようになるには繰り返しが不可欠、といった内容が記されている。どちらにも効果はあるのだが、どちらがより効果的なのだろうか。
この問いに対する答えを探るため、プリンストン大学の研究(2018年3月)では、コンピューターを用いて架空のマウスの動きをシミュレーションし、生物が「報酬」によって行動を変えるのか、あるいは「反復」によって行動を維持するのかを検証した。
このシミュレーションの結果、決定的に重要なのは「反復」となった。デジタルマウスたちは、報酬が途中で途絶えた状況においても、これまで行ってきた行動を淡々と続けたのである。つまり、本来の目的や報酬がなくなったとしても、反復によって培われた行動の勢いは失われないことが示された。つまり、習慣を形成する際に「継続的に行動を繰り返すこと」が最も重要であることが理解できるだろう。
習慣形成に必要な65日(基準)
では、新しい習慣を作るには、どのくらいの時間が必要だろうか?ウッド博士の研究によると、平均して 65日間 が目安だとされている(参考著書:良い習慣、悪い習慣(Good Habits, Bad Habits))。
ウッド博士の研究室で行われた実験は、研究チームが参加者は、参加者に「新しく習慣にしたい健康行動」を選ばせ、それが自動化するまでの期間を追跡した。例えば、「昼食に果物を1個食べる」や「夕食の直前に15分間運動する」などの行動である。結果として、以下の傾向が確認された。
- 水を飲む:59日
- 健康的な食事をする:65日
- 運動をする:91日
ある行動を習慣化するためには、平均して65日間の繰り返しが必要である。また、簡単な行動なら約2か月で習慣化できるが、行動が複雑になるほど、その期間は長くなってしまう。つまり、食生活の改善や運動、睡眠など、複数の要素が絡む習慣を作る場合は、もう少し長い期間を見込んだ方が良いだろう。
65日(約2か月)という期間を聞くと、少しハードルが高く感じるかもしれない。しかし、この研究では、参加者が1日や2日ほど休んだとしても、それが大きな問題にはならないことが示されている。あまり厳格になりすぎず、時には柔軟に取り組むことも、習慣を定着させる上でのポイントとなるだろう。
「ナンバーマジック4」の法則
習慣化には期間だけではなく、頻度も重要である。ビクトリア大学の研究(2015年8月)では、ジムに加入したばかりの男女111人を対象に、12週間にわたって「ジム通いが続く人と続かない人の違い」を調査した。研究の目的は、「ジム通いが続いた人と続かなかった人にはどんな違いがあるのか?」を明らかにすることであり、この結果、ジム通いを成功させる鍵が「頻度」であることが示された。
調査では、年齢や生活習慣といった個人差を考慮しても、ジムに行く頻度 が習慣化の最大の要因であることが判明した。1週間にジムへ行く回数が多いほど、その後もエクササイズを続けられる確率が高くなっていた。特に、研究の結果として見えてきたのが 「週4回以上」 のジム通いが習慣形成にとって重要だということである。この結論は一見当たり前のように思えるが、「繰り返しの回数を増やすほど習慣になる」という事実を明確に証明した意義があるだろう。
さらに、この研究にはもうひとつ注目すべきポイントがある。それは「マジックナンバー4」だ。週に4回以上ジムに行くと、エクササイズが習慣化される可能性が大きく跳ね上がる。逆に、週に3回以下しか行かない人は、習慣が続かなくなる傾向が強くなってしまう。
具体的なデータでは、どちらのグループも 最初の6週間までは 同じように習慣化の確率が上がっていく。しかし、週4回未満のグループは、6週目を過ぎると12週間目にかけて徐々に習慣化が失われ、最終的にはエクササイズ習慣が身につかない状態に戻ってしまった。つまり、6週間目の壁を超えるためには、最低でも週4回以上のトレーニングが必要になる。
習慣化に関するもう一つの興味深い研究として、ロンドン大学の調査(2009年7月)が参考になるだろう。この実験では96人の学生に「新しい習慣を身につける」課題を与え、エクササイズや勉強がどのくらいの期間で「歯磨きのように自動的にできる行動」になるかを調べたものだ。
①習慣化は最初が最も難しいが、時間が経つと簡単になる
研究では、習慣化までの期間は平均で50~60日必要である。25日目まではあまり習慣化しないものの、8週間を超えると自動的にできるようになる傾向が強い。
②難しいタスクほど、習慣になるまで時間がかかる
シンプルなウォーキングの場合、習慣化までに約25日間が目安となる。一方で、毎日腹筋50回といった少しハードなトレーニングでは、約60日かかるという結果が出た。
これらは前述のウッド博士の研究結果とも重なる。指標として新たな習慣を確立するためには、最低でも2ヶ月以上の期間を設けることが望ましいだろう。
睡眠のために、具体的に何を習慣化すべきか
以下の内容を習慣化し、生活に取り入れることで、自然と良質な睡眠が得られるようになり、疲労回復のスピードが向上するだろう。 最初は窮屈に感じられるかも知れないが、少しずつでも続けていくことが重要である。
必須事項
- 起床時間の7〜8時間前を就寝時間に固定する(決定する)
- 「決めた睡眠時間を死守」を生活の再優先事項にする
- 睡眠前の1時間は本を読む、ストレッチをするなど、神経を落ち着かせる活動を取り入れる
- 朝から昼間までに最低15分は太陽光を浴びる
運動・食事
・日常的なウォーキングやNEAT(非運動性熱産生)を増やす
エレベーターの代わりに階段を使う、通勤の際に少し歩く距離を増やすなど、無理のない範囲で身体を動かす工夫をする
・厳しいバージョンの有酸素運動、HIIT(高強度インターバルトレーニング)やSIT(スプリントインターバルトレーニング)などを実践する
・オメガ3や中鎖脂肪酸といった健康的な脂肪の摂取を増やす
良質な脂肪は、身体の炎症を中心に効果があり、全体的な健康と睡眠の質を向上させる
・適切な炭水化物の摂取
摂取量が多すぎても少なくても睡眠に悪影響を及ぼす
・GABAを増やす食品を摂る
たまねぎ、にんにく、ブロッコリーなどには、睡眠を促進する効果が期待されるGABA(γ-アミノ乳酸)が多く含まれている
・間食は厳禁
無駄にインスリンが分泌される可能性がある
・就寝前の食事は厳禁
理想的には就寝の4〜5時間前には夕食を済ませるようにし、就寝前2時間以内の食事は控える
・就寝前のアルコールは厳禁
一時的にリラックス効果をもたらすが、睡眠の後半の質を下げ、深い眠りを妨げる
・午後のカフェインは厳禁
覚醒効果があり、摂取後数時間以上体内に残るため、寝つきを悪くし、睡眠全体の質を低下させる
体内時計
- 朝から昼間までに最低15分は太陽光を浴びる
- 日中は必ずカーテンは全開にし、自然光を取り入れる
- 夜は室内の照明は最低レベルまで落とす
- 夜はスマホやPCなど、デジタルデバイスの画面の輝度を下げる
- ふとんやベッドの上では読書やゲームなどは厳禁、睡眠のための場所として体に認識させる
- 深夜に目が覚めたとしても気にしすぎないようにする(狩猟採集民の時代は二度目が普通だった)
- 前日に十分な睡眠が取れなかった場合は、短時間の昼寝(20〜30分程度を目安)を取り入れる
復習:アイテム編
- マットレス:自分に合ったものを探す
- 枕:自分に合ったものを探す
- ブランケット:重いと良い
復習:環境編
・光:寝室を暗くする(5ルクス以下)
①遮光カーテンに切り替える
②電子機器のLEDライトなど、夜中はすべての光源をカット
・温度:室温は摂氏15~20度の範囲内
・音:各種ノイズ、もしくは耳栓を活用する
まとめ:疲労回復と睡眠 #3【習慣編】
疲労回復のために質の高い睡眠を得るには、正しいアイテムや環境の準備だけでなく、日々の習慣の積み重ねが欠かせない。習慣を形成するためには、反復が何よりも重要であり、少なくとも2か月間、着実に行動を続けることが推奨されている。
具体的には、就寝時間を固定する、夜間の食事やカフェインを避ける、体内時計を調整するための朝の太陽光を浴びるなど、どれも健康的な睡眠習慣の確立に役立ってくれる。また、適切な運動や栄養の摂取は、疲労回復を助けるだけでなく、睡眠の質を向上させる要素である。
習慣の定着は難しいと感じるかもしれないが、週4回以上の頻度で取り組み、最低2ヶ月を目安に続けることで、より良い眠りと健康な生活が期待できるだろう。
最初は難しく感じられるかもしれないが、自分のライフスタイルに合わせた無理のない範囲で、少しずつ改善を重ねていけば、結果的に自然な睡眠習慣が身につき、競技パフォーマンスの向上や日常生活の質の向上にもつながっていくだろう。ぜひ、挑戦してみて欲しい。
【参考文献】
(Amazon)トレーニングとリカバリーの科学的基礎
(Amazon)不老長寿メソッド