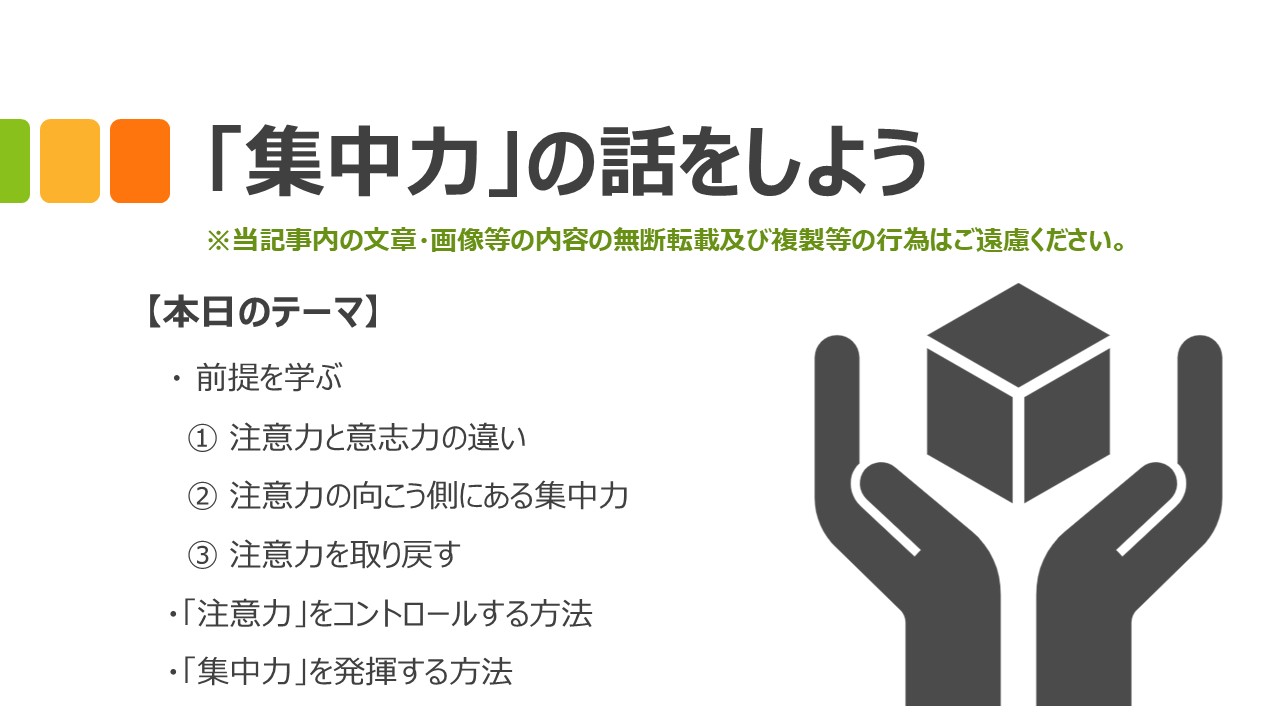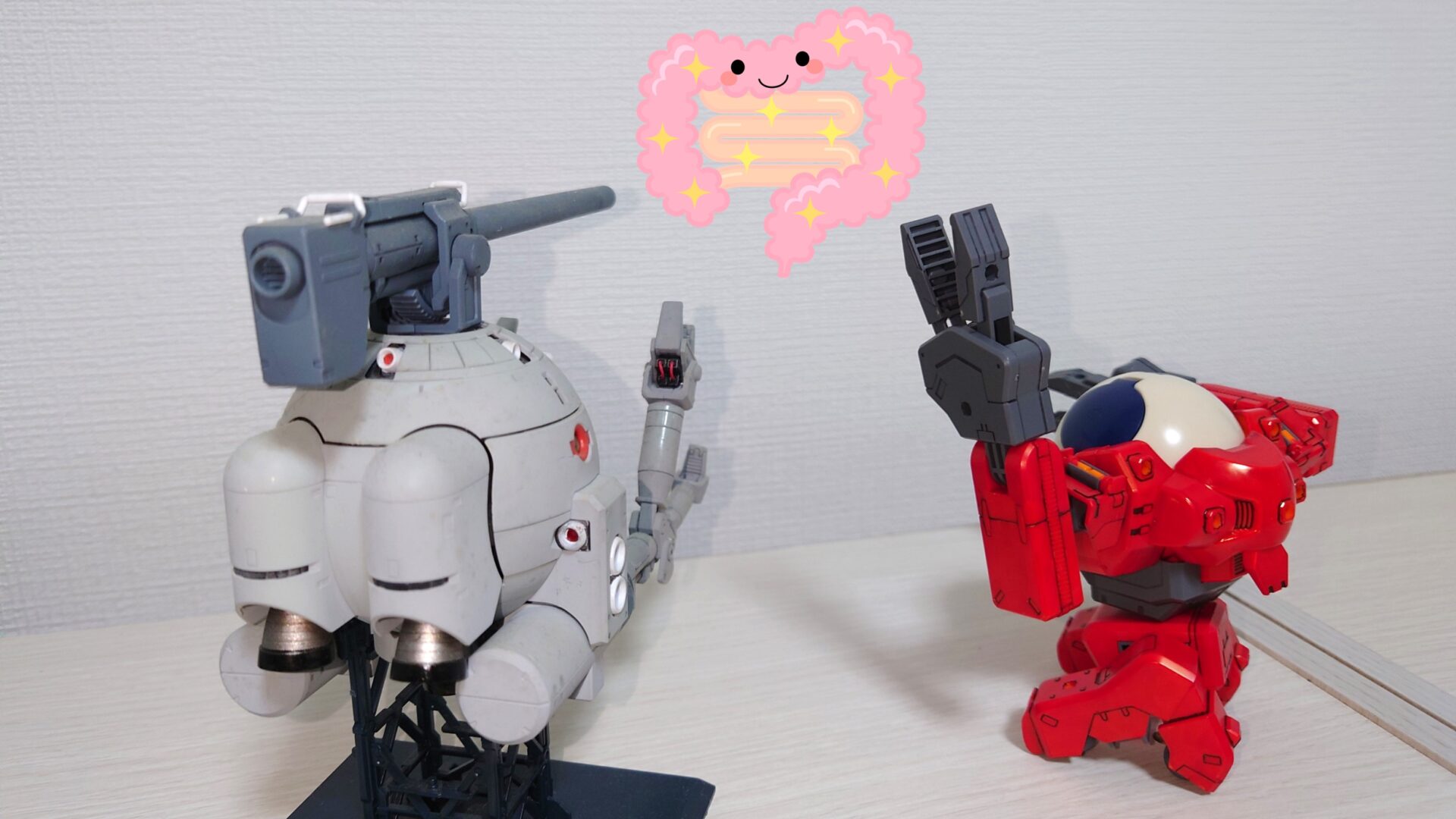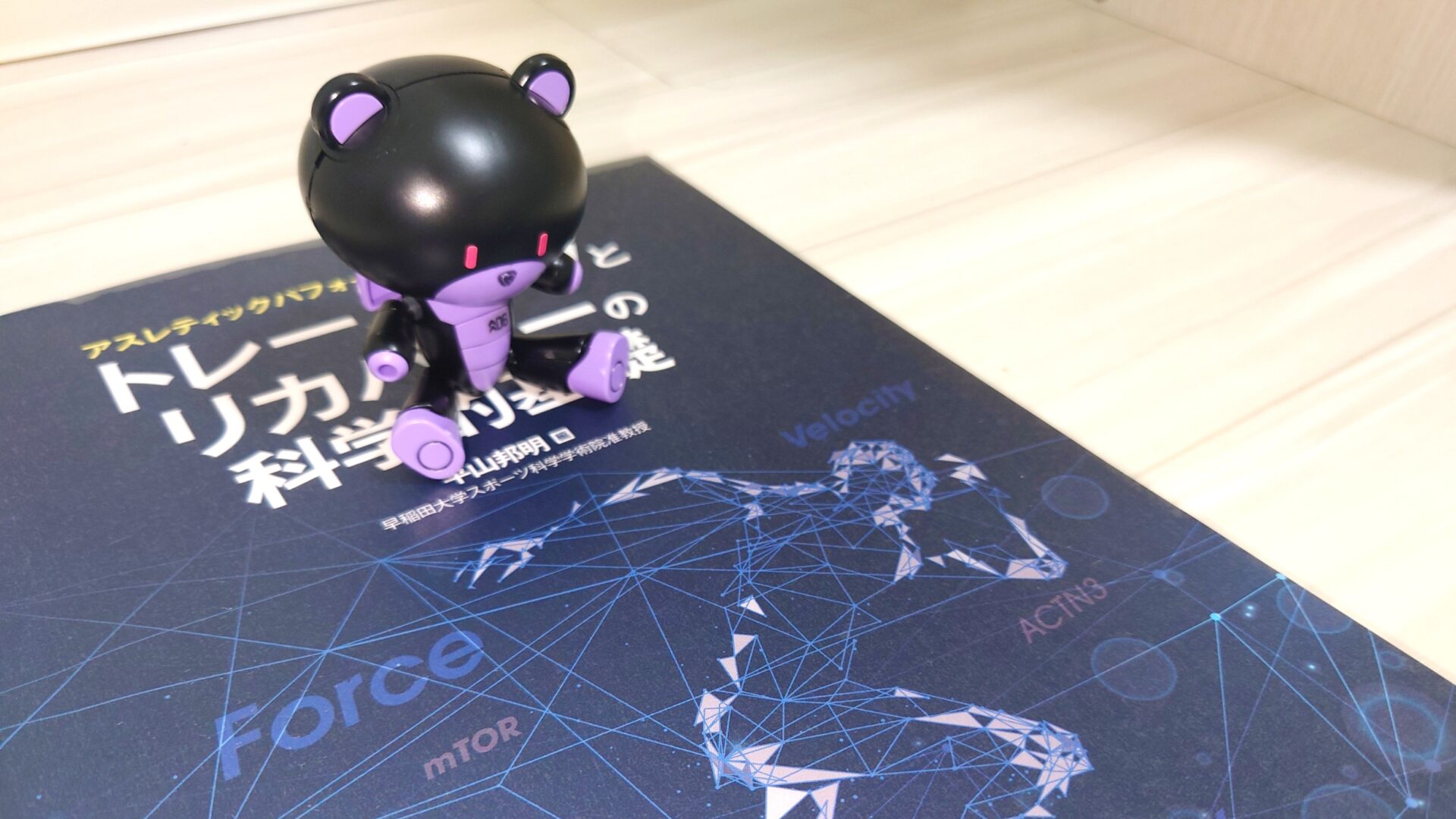集中力の育て方 #2【初級編:ネットファスティング】

集中力を高める近道は、週に一度の「ネット断ち」を習慣化すること。まずは数時間から始め、通知やデバイスを物理的に遠ざけ、代替行動(読書・運動)に置き換えると継続しやすく効果が出るだろう。
集中力の育て方 #2【初級編:ネットファスティング】
前回の記事『集中力の育て方 #1【初級編】』では、「デジタルデバイスを片付ける」「ニュースダイエット」という集中力向上のための方法を紹介した。今回は、さらに一歩進んで、集中力を覚醒させる「ネットファスティング」に挑戦してみて欲しい。
「ネットファスティング」とは、簡単に言えば、週に一度、インターネットから離れる日を設けることである。デジタルデバイスを使わない時間を意図的に作ることで、集中力を取り戻し、生産性を高める可能を広げるだろう。
競技会や大会で集中できない、隣のレーンが気になる、観衆が気になるといったメンタルの問題を抱えている方にとって、ネットファスティングは集中力を高める有効な方法となる。なぜならば、集中力が向上すれば、競技力の向上につながるからだ。
なぜネットファスティングがオススメなのか?
前回の集中力の記事で書いたとおり、我々の最終的な目標は、自分の意思でゾーンに入り、フロー状態を作り出すことである。しかし、ネットサーフィンとフロー状態は、脳の働きとしては真逆の状態にある。つまり、日常的にネットサーフィンを習慣にしていると、フロー状態に入ることが難しくなってしまうのだ。
ネットファスティングを通じて、脳の習慣をリセットし、フロー状態に近づくための新しい習慣を身につけることが目指すべきポイントである。
そもそも、悪い習慣を断ち切るのはかなり難しい。悪い習慣をやめるためには、良い習慣で上書きするのが、科学的に効果のある方法だとされている。「ネットサーフィン」という悪い習慣を、「ネットファスティング」という新しい良い習慣で上書きして欲しい。そして、集中力を取り戻し、自分自身をコントロールするための一歩として、ぜひ取り組んでみて欲しい。
ネットファスティングを始める前に
「ネットファスティング」と聞くと、なんとなく「やりたくないな」と思う方も多いだろう。そこで、少し視点を変えてみる。まず先に、新しい良い習慣を身につけるための原則を紹介する。この原則を活用すれば、ネットファスティングにも少しずつ楽しく挑戦できるだろう。
① 習慣は目標に依存しないが、最初は強い目標を設定する
基本的に、良い習慣は、ある目標に向かって、ある特定の状況下で同じ行動をくり返すことによって形成される。そして、時間が経つにつれて、その行動は目標に依存しなくなる。
例えば、「もっとモテたい」「健康の質を上げたい」など、習慣を始める目的をしっかりと考える。最初のうちはその目標を強く意識し、少しずつその目標が意識から消えても続けられるようにしていく。
つまり、習慣を形成するためには最初の目標の設定が欠かせない。目標はあくまできっかけであり、最終的には自然に行動が身についていくことを目指そう。
② 自分の文脈を理解する
良い習慣を身につけるためには、できる限り一貫性を保たねばならない。まず自分の「悪い習慣」がどのような状況で発生するのかを知り、状況を把握しておこう。習慣は、特定の状況(文脈)で繰り返し行われることで形成される。悪い習慣を改善したいときは、自分が反応する文脈を理解しておくのが有効だ。例えば、「夜にベッドに入るとついスマホを見てしまう」「通勤中にSNSをチェックする」などが、自分の文脈となっている。
また、この観点からすれば、時間ベースの習慣化(例:午後9時に運動する)よりも、出来事ベースの習慣化(例:会社が終わったら運動する)のほうが文脈が強く効果が大きい。自分の文脈を理解した上で、自分を動かす文脈で対策を立てていく。
③ 事前のトラブル対策を考える
習慣の形成には繰り返しが不可欠だが、必ずしも順調に進まないこともあるだろう。そのため、あらかじめどのようなトラブルが起きるかを想定し、対策を考えておくことが重要だ。例えば、「ジムに行こうと思ったら、食事に誘われた」や「帰宅して勉強しようと思ったら、残業をしなければならなくなった」などのように、あり得るトラブルを事前に想定しておく。
食事に誘われたら、「ジムに行ってから合流する」。残業を命じられたら、「残業分の勉強ができる日に、リスケジュールをする」。簡単な対策であっても、何も準備をしていないと、トラブル時にうまく対処できる人は少ない。また、リマインダーを活用する。ただし、リマインダーの効果は時間とともに低下(例:時間が経つと、机の上の付箋に気づかなくなる)していくことも認識しておく。
④ 習慣は自動的である
悪い習慣がなかなか断ち切れないのは、それが自動的に行われているからである。習慣は意識を必要とせず、多くの場合、習慣がスタートしたことすら気づけないことが多い。そのため、自分の文脈を理解すると同時に、自分が行った行動だけでなく、行動を起こすトリガーに注意する。
例えば、「ついコンビニスイーツを食べてしまう」「イライラして買い物をしすぎてしまう」など、自分の悪い習慣が起きる前に、どんなトリガーがあったのかを意識しておくとよい。「コンビニに寄ってスイーツを買うのは、友人に会ってスイーツトークを聞いたとき」なので、「スイーツトークを聞いた後はコンビニ寄らず、スーパーで健康に良い食材を探す」や「イライラして買い物に出掛けるのは、仕事で嫌なことがあったとき」なので、「仕事で嫌なことがあった後は買い物には行かず、ジムに行って汗を流す」など、トリガーで引き起こされる悪い習慣を良い習慣に変えてしまおう。
⑤ 報酬を設定して楽しむ
人間は報酬を求める生き物である。報酬は行動を強化し、習慣の形成を促進してくれる。ネットファスティングを実践した日には、自分に対して小さなご褒美を設定するのも一つの方法である。
例えば、「好きな映画を見る」「好きな物を食べる」など、自分が喜ぶことできるものなら、なんでも報酬として機能する。なお、報酬はいつも与える(連続強化)や回数ベース(数回に1回の割合で発生する)ではなく、飛び飛びに間隔を空けて与える(部分強化)や期間ベース(一定期間が過ぎたら発生する)ほうが効果が高い。
⑥ 習慣は時間をかけて形成される
当たり前だが、習慣作りには時間がかかることを覚えていて欲しい。研究によれば、習慣の形成には18日から254日かかると言われており、難しいものほど時間がかかってしまう。
そのため、新しい習慣を作るときは、一度にひとつの習慣を形成することに集中しなければならない。
実践:ネットファスティング
① ネットファスティングの目的を理解する
最初に、あなたのネットファスティングの目的を明確にしておく。これは単に「インターネットを使わない」という制限を課すためではなく、集中力を高め、自分自身の生活の質を向上させるためのものである。目的を意識することで、ネットファスティングへのモチベーションが維持しやすくなるだろう。
② 週に一度、インターネットの使用を控える
最初から一日中インターネットを使わないことが難しいと感じるはずだ。この場合は、一日数時間から始めてみよう。例えば、毎週日曜日にネットファスティングを試し、徐々にその時間を延ばしていく。
③ ネットファスティング中に集中力を高める活動をする
ネットファスティング中は、インターネットに代わる活動を見つけよう。読書、瞑想、運動、趣味など、自分が楽しめる活動や新しいスキルを習得する時間にするのが理想的である。これにより、ネットの誘惑を断ちつつ、集中力をさらに高めることができる。
④ しっかり気持ちに向き合う
ネットファスティング中には、「今、インターネットを使いたい」と強く感じることがあるだろう。そのときは、その気持ちを無視せず、自覚して観察することが大切だ。「なぜ今、ネットを見たくなったのか?」と自問し、自分の感情に向き合うことで、より冷静に対処できるようになっていく。
⑤ しっかり振り返りを行う
ネットファスティングが終わった後は、必ず振り返りを行う。具体的にどのように過ごし、どんな変化を感じたのかを記録することで、自分にとっての効果を実感しやすくなる。そして、この振り返りを次のネットファスティングへのモチベーションにつなげていく。
⑥ 習慣化する
ネットファスティングを継続的に行うことで、集中力と生産性を着実に向上させることができる。少しずつでも続けていくことで、脳が新しい習慣に適応し、良い影響が長期的に現れることだろう。
まとめ:集中力の育て方 #2【初級編:ネットファスティング】
なぜネットファスティングをすべきなのかを、もう一度思い出して欲しい。
我々の最終的な目標は、自分の意思でゾーンに入り、フロー状態を作り出すことである。しかし、ネットサーフィンとフロー状態は、脳の働きとしては真逆の状態にある。つまり、日常的にネットサーフィンを習慣にしていると、フロー状態に入ることが難しくなってしまう。
ネットファスティングを通じて、脳の習慣をリセットし、フロー状態に近づくための新しい習慣を身につけよう。「ネットサーフィン」という悪い習慣を、「ネットファスティング」という新しい良い習慣で上書きして欲しい。そして、あなたが持っている「真の集中力」を取り戻し、心も身体も思うがままにコントロールできるようになってもらいたい。
【参考文献】
(Amazon)NEWS Diet
(Amazon)ヤバい集中力
(Amazon)超人の秘密 エクストリームスポーツとフロー体験