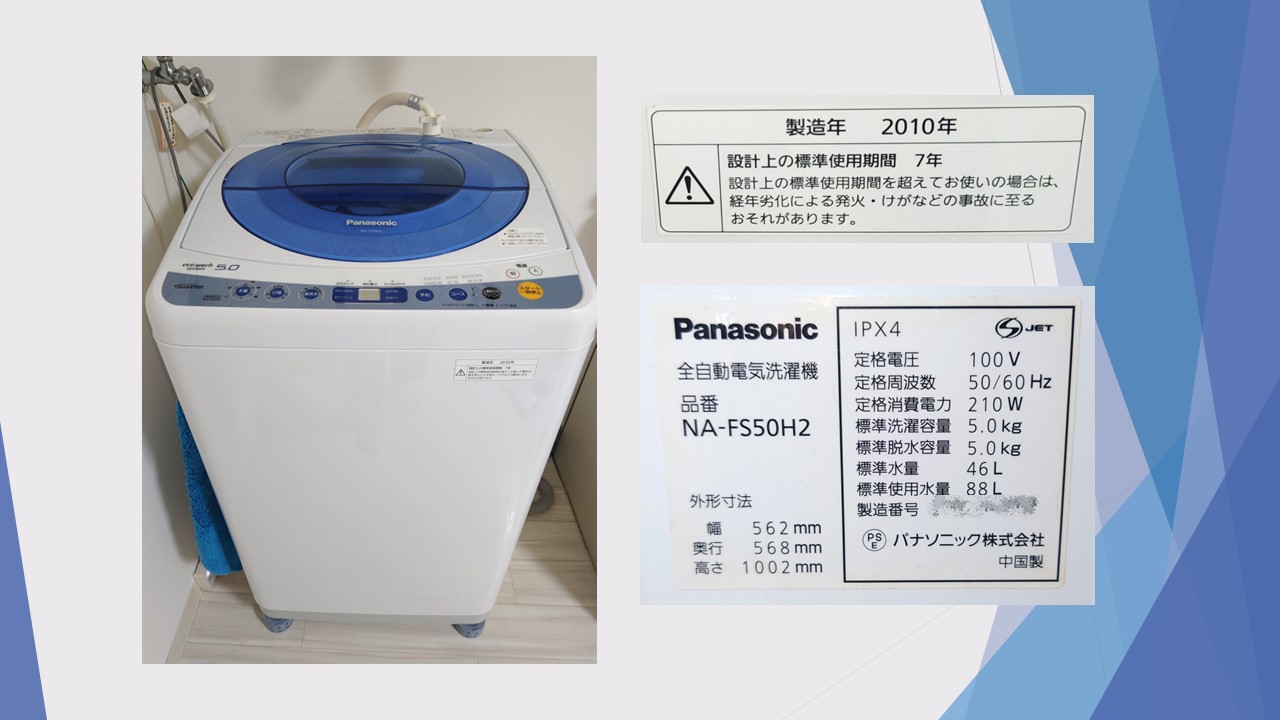ドアノブ・ラッチ編【ご長寿シリーズ】

ドアノブが動かなくなったら、まずはラッチの確認と交換が解決の近道です。賃貸なら管理会社に依頼が基本ですが、自己責任でのDIYならプラスドライバー1本で作業できます。
ドアノブ・ラッチ編【ご長寿シリーズ】
ある夜、居間から出ようとドアノブを押し下げたところ、「カチャン」と小さな音がしました。しかし、何かが落ちた様子はありません。まさかと思いながらドアを押してみると、開きません。
「まさか脱出不能?」と思いましたが、ドアレバーを上方向に引き上げると、ラッチが引っ込み、ドアは難なく開きました。しかし、これでは毎回面倒ですし、もし逆方向も壊れたら、まさかの「閉じ込め」状態になってしまうかもしれません(苦笑)。
そこで今回は、ドアノブ・ラッチ交換に挑戦した記録を紹介します。
- ラッチ寸法を測る
- ラッチを交換する
ラッチ寸法を測る
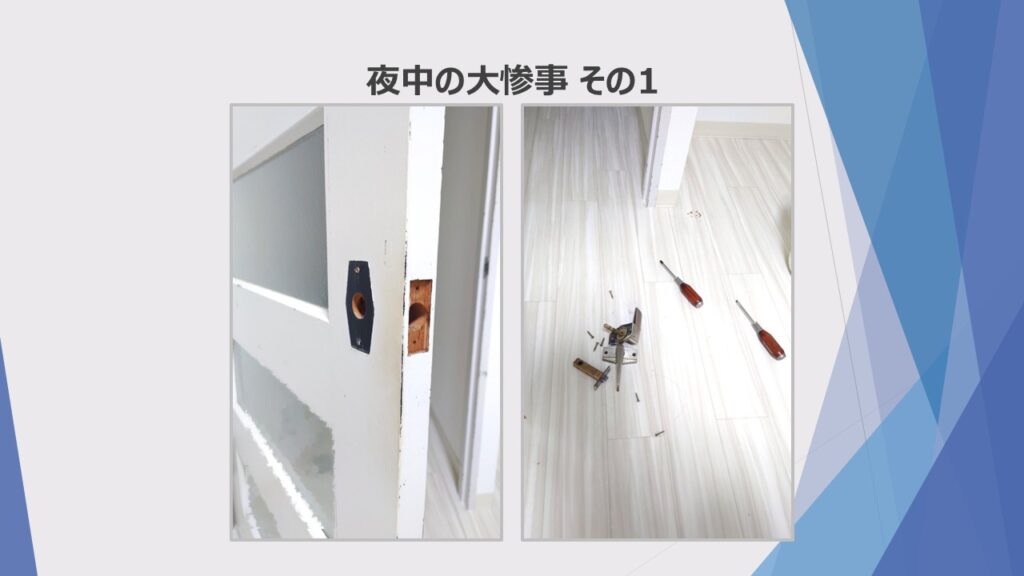
本来であれば賃貸物件なので、管理会社に連絡して修理を依頼すべきです。
賃貸物件の修理依頼
- 管理会社に連絡する
- 現状を確認してもらう
- 部品を発注してもらう
- 部品が届いたら、修理してもらう
という流れですが、正直なところ待ち時間が長くて面倒に感じてしまいました。
そこで、思い切って自己責任でDIYに踏み切りました。必要な道具は、プラスドライバー一本だけです。費用を抑えられ、時間の節約になります。とはいえ、完全なる自己責任です!修繕ミスやさらなる故障は修繕費の自己負担が発生します!ご注意ください!!
まず、ドアノブを取り外してみました。分解してみると、ラッチ内部の可動部が壊れていることが判明しました。構造上、修理は難しいため、新しいラッチを購入することにしました。
この部品の購入で重要なのは、サイズをしっかり測ることです。この手の部品には様々なサイズがあり、規格が合わないと交換できません。特に、ラッチの凹凸部分(鎌型部分)がきちんとかみ合わないと、永久にドアが開かないままです(笑えなくなるやつですね)。
ラッチ寸法の測り方
- ドアノブを外す~ドアノブを外してラッチ部分の寸法を測ります。必要な寸法は「ラッチの長さ」と「ラッチの奥行き」
- ラッチの形状を確認~ラッチの凹凸部分(鎌のような形状)が合うか確認する。この部分が合わないと、交換できてもドアがスムーズに開かなくなってしまう。
我が家では「SHOWA製」ラッチがついていましたが、同じ規格が見つからなかったため、互換性のある「川口技研」の交換用ラッチを注文しました。約1週間後に、新品部品が到着しました。
ラッチの交換
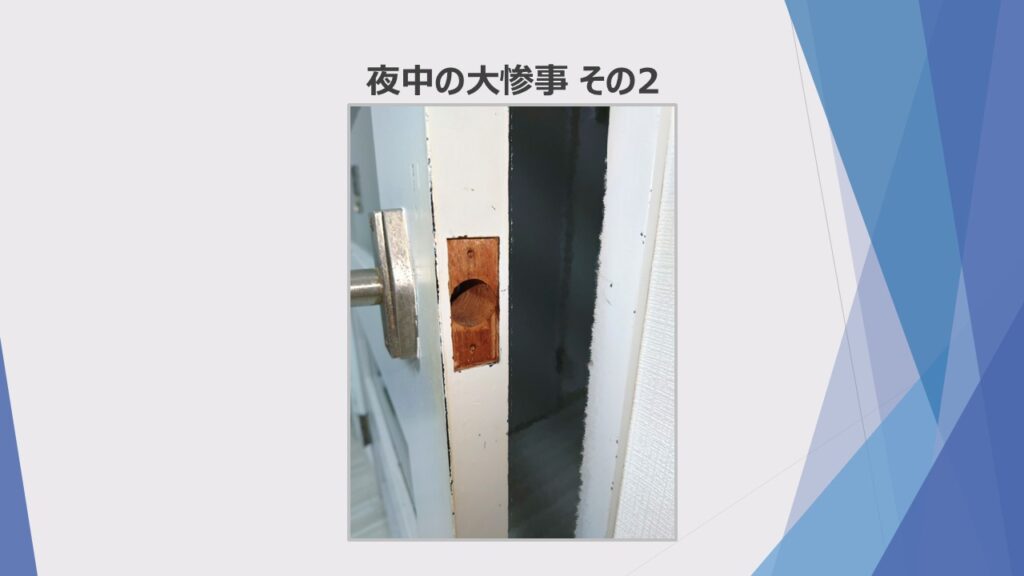
部品到着までの間は、片側だけドアノブをつけて使用しました。片側だけでも開閉は可能でしたが、いつもほんの少しだけドアが開いた状態なので、冬にはちょっと厳しい一週間でした。
ラッチが届いた後は、交換作業の開始です。作業時間は、およそ10分。使用工具は、プラスドライバーが一本。手順はいたってシンプルです。
ラッチの交換作業(約10分)
- 古いラッチを外す(我が家は外しっぱなしだった)
- 新しいラッチをつける
- ドアノブを元に戻す
せっかくドアノブをすべて外したので、金属磨き「ピカール」でお手入れしました。私が大好きな「ピカール」は、布に少量つけて磨くだけで、くすんだ金属が新品同様に輝きます。

ピカールの使い方
- ドアノブの表面をきれいに拭く
- ピカールを少量取り、柔らかい布で磨く
- 仕上げにもう一度拭き取り、乾拭きすれば、驚くほどきれいになる
綺麗になったドアノブを見ると、「モノを大切にしている」という実感が湧き、気分まで晴れやかになります。もちろんドアノブ以外、鍋や自転車などの金属部品にも応用できるのでおすすめです。
まとめ:ドアノブ・ラッチ編【ご長寿シリーズ】
ドアノブ・ラッチの交換は、賃貸物件では管理会社に修理を依頼すべきですが、対応に時間かかることもあります。しかし、正しいサイズの部品さえ入手できれば、工具一本で誰でもできる簡単なDIY作業であることも確かです。
日常の小さなトラブルでも、工夫と手入れで生活は快適になります。あくまでも、自己責任の範囲内で挑戦してみるのも良いでしょう。
・参考アイテム
(Amazon)レバー用ラッチ ラッチ本体のみ【川口技研】
(Amazon)ピカールネリ 250G【日本磨料工業】